宝馨会長(日本高野連)の経歴とは?
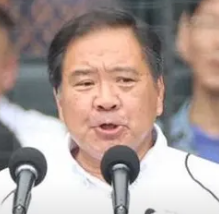
日本高野連の宝馨会長の名前を聞いて、「誰?」と感じた人もいるかもしれませんが、実は日本の防災・教育・野球の現場で長年活躍してきた超マルチな人物です。
ここでは、年齢や出身地といった基本情報から、どんな経歴をたどってきたのかをわかりやすく紹介していきます。
読み進めれば、なぜ京都大学の名誉教授が高校野球のトップに立つことになったのか、納得するはずです!
出身地や年齢、生年月日などの基本プロフィール
宝馨さんは1957年2月12日生まれで、現在68歳(2025年時点)。
出身地は滋賀県彦根市です。
「寶馨」と書いて「たから かおる」と読むこの名前、字面だけでもなかなかインパクトがありますよね。
ちなみに、旧字体の「寶」は“宝”の昔の字。ニュースなどでは「宝馨」と書かれることもあります。
宝馨さんの家系についても後で紹介しますが、平安時代までさかのぼる由緒ある姓だとか。
歴史好きにはたまらないロマンを感じるところです。
そうそう、68歳とは思えないバイタリティで、会見でも自ら英語で通訳をしたりと現場に立ち続けている姿が印象的。
システムエンジニアとして会議通訳の英語に悶絶した記憶がある身としては、「普通じゃないなこの人…」とつい尊敬の目で見てしまいます。
この先の章では、そんな宝馨さんがどんな専門家だったのか、詳しく見ていきます!
次は、工学博士としての実績や、名だたる機関との関わりについて深掘りしていきましょう。
防災と土木の専門家としてのキャリアと受賞歴
宝馨さんは、京都大学工学部で土木工学を学んだあと、なんとそのまま京都大学の助手、教授とキャリアを積み重ね、ついには名誉教授の称号を持つまでに至ったガチ中のガチな研究者です。
専門は水文学・水資源工学・防災政策といった「水」と「災害」にまつわる分野。
特に、洪水リスクや再現確率などの「極端気象への統計的対処」をテーマにしていて、日本全国の河川の防災計画に宝馨さんの研究成果が使われているほどの人物です。
個人的に印象に残ったのは「SLSC」や「ジャックナイフ法」など、なんだかSEのアルゴリズムっぽい手法を土木に応用していること。
これ、データと現場の両方が分かってないと使いこなせないやつです。
それだけでなく、国際的な場でもバリバリ活躍されていて、ユネスコ、水文・水資源学会、日本学術会議など、50以上の機関で要職を歴任。
さらに「防災科学技術研究所」の理事長も務めており、日本の災害対策の最前線にも身を置いています。
受賞歴も、土木学会論文賞やユネスコの表彰、海外の学術賞など多数。
いやもう、ここまでくると「ただの研究者」なんて言葉じゃ全然足りません。
防災の理論を現場に落とし込める希少な人材であり、教育者としても48人の博士を育てた実績があるんです。
この“バリキャリ研究者”が、なぜ高校野球に関わるようになったのか…
その背景には、ちょっと驚きの野球愛が隠されているんです。
宝馨会長の学歴がすごい!京都大学で防災の研究者に
宝馨さんの学歴は、いわゆる“エリート街道まっしぐら”タイプ。
ただの優等生ではなく、その知識を社会に活かす実践型のキャリアが特徴です。
ここでは、幼少期から大学、そして京都大学での研究者時代まで、彼の歩みを振り返っていきます。
なぜ日本高野連のトップが「工学博士」なのか?読めば納得の背景が詰まってます!
出身高校・大学〜大学院までの学歴まとめ
まず、小学校は滋賀県彦根市でスタート。
その後、京都市、近江八幡市、西宮市と、あちこちを転校しながら育っています。
中学は西宮市立大社中学校を卒業し、進学先は兵庫県立西宮北高等学校。
ここで硬式野球部に所属していたことが、後の人生に大きく影響を与えることに。
高校卒業後は、京都大学工学部土木工学科に進学。
さらに大学院にも進み、1981年には修士課程を修了、1990年には京都大学から工学博士の学位を取得しました。
個人的に思うのは、京大で“水”にまつわる研究を始めたのが、まさに地球規模での防災のスタート地点。
土木という分野の中でも「水の流れ」や「災害対策」という切り口は、これからの気候変動時代に超重要。
そんな未来を30年前に先読みしていたあたり、宝馨さんの視野の広さを感じずにはいられません。
このあと紹介する「名誉教授」や「ユネスコの防災責任者」などの肩書きも、ここが原点になっているんです。
では続いて、京都大学でどんな研究活動をしてきたのかを深掘りしていきます!
京都大学での研究実績と名誉教授としての功績
京都大学では、防災研究所を中心に約30年近く在籍。
助手、助教授、教授とステップアップし、最終的には名誉教授の称号を授与されました。
専門は「洪水リスクの数理モデル」や「水資源の最適管理」など、実に実践的なテーマ。
日本の河川の防災設計で使われる統計モデルに、宝馨さんが開発した手法が今でも活用されているんです。
さらにユネスコの国際水文学計画や、国連の防災活動にも長年関わり、東南アジアの防災支援なども実施。
ここまでくると、学者というより「国際防災プレイヤー」と言った方が近いかもしれません。
ユネスコから表彰を受けたこともあり、京都大学に「ユネスコチェア」を設立した実績もあります。
これ、京大初の快挙だったとか。
理論だけじゃなく、現場や教育にも力を入れていて、博士号取得者を48人も育てているというから驚きです。
こんな教授、身近にいたら絶対刺激的だろうな…と思わずにいられません。
次は、そんなアカデミックな宝馨さんが「野球」にどう関わってきたのかを見ていきます!
宝馨会長は野球にも情熱を注いできた!
京都大学の教授というと、なんとなく研究室にこもって難しい論文を書いてそうなイメージ、ありますよね。
ところが宝馨さんは、そんな学者の枠を飛び越えて、野球というフィールドでも全力投球してきた人物なんです。
ここでは、その熱すぎる“野球愛”を紐解いていきます!
京都大学硬式野球部での活動と監督エピソード
実は宝馨さん、学生時代からずっと京都大学硬式野球部に所属していました。
しかも、ただの部員ではありません。
卒業後はコーチ、監督、副部長、そして部長まで歴任し、最終的には京大野球倶楽部の会長にもなっています。
とくに監督を務めた2013年〜2014年には、京大初のプロ野球選手である田中英祐さん(後にロッテへ)の指導者としても知られています。
このあたり、ただの“野球好きなおじさん”とは次元が違います。
エンジニア的な観点から見ると、「教育」「育成」「マネジメント」「戦略分析」…といった組織運営スキルが、野球部の現場でも活かされていたんじゃないかと推測できます。
実際、部員に向けた言葉やエピソードを見ると、いち研究者というより“信頼される監督”の顔が見えてくるんですよね。
そういった地道な活動が評価され、2021年には日本高等学校野球連盟(日本高野連)会長に就任することに。
ここまで読んできて、「あ、なるほど。だからか」と思った人も多いはずです。
では、宝馨さんが現在どんな活動をしているのか、もう少しだけ深掘りしてみましょう!
日本高野連会長就任と現在の活動内容とは?
日本高野連の会長に就任したのは、2021年12月のこと。
元々、高校野球や学生野球の教育的意義に深く関わってきた経歴から選ばれた形です。
現在は、全国高校野球選手権(夏の甲子園)の総括や制度改革の発言も積極的に行っていて、たとえば2025年夏には広陵高校の暴力問題について記者会見で「異例の謝罪」をしたことが話題になりました。
その場面では、通訳が来ない緊急事態の中で宝馨さん自身が英語で通訳役を務めるという神対応もあり、ネットでは「会長すごすぎ」「万能か」と称賛の声が上がっていました。
こうした姿勢を見ると、データや知識だけではなく、現場の空気を読む力やリーダーシップに長けた人物だとよくわかります。
防災と野球、一見関係なさそうに見える2つの分野を、宝馨さんは「人を守る」という軸でつないでいるのかもしれません。
最後に、彼のルーツや家族についても触れておきましょう!
宝馨会長の家族構成や名字のルーツとは?
防災の専門家であり、野球部監督であり、そして高野連会長。
ここまで見てくると、宝馨さんが「どんな家庭環境で育ったんだろう?」と気になってきませんか?
この章では、名前の由来から家族情報まで、宝馨さんのプライベートにグッと迫ります!
宝馨の「寶」姓の由来が歴史的にすごい
まず注目したいのが「寶馨」というお名前の“寶”の字。
これは「宝」の旧字体で、なかなかお目にかかれない漢字です。
実はこの“寶”姓、平安時代まで遡るルーツがあるんです。
第55代文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が近江(現在の滋賀県)に隠棲していた時、先祖が皇族の宝物庫を管理する役割を担っていたことから、この名字を授かったと言われています。
…って、これもはや歴史の教科書案件では?
滋賀県米原市の榑ヶ畑(くれがはた)という廃村にその伝承が残っており、宝馨さん自身が生まれた彦根市からも近い場所です。
名字にそんな由緒があるなんて、ちょっとロマンありますよね。
40代SEとしては、名刺交換のときにこういう雑学をそっと差し込んでくる人、めちゃくちゃ好きです(絶対話が弾むやつ)。
名字ひとつでここまで深掘りできる人、そうそういません。
家族構成やプライベートの情報は?
残念ながら、家族に関する詳しい情報は公開されていません。
奥様やお子さんに関する記述も見つからず、かなりプライベートは厳重に守っている印象です。
ただし、家庭を大切にしているタイプだろうな…というのは、言葉遣いや立ち居振る舞いからも伝わってきます。
あと、学生や若者に対する接し方がとても柔らかくて、怒鳴ったり威圧したりするタイプではなさそう。
SNSでの発言やエピソードからも、柔和な性格がにじみ出ています。
「地位が上がるほど腰が低くなる」という理想形を体現してるんじゃないでしょうか。
高野連の会長として、今後も若者たちの未来を後押しする存在であり続けてほしいですね!
