渋谷陽一(ロッキングオン)さんが死去:死因は脳出血からの誤嚥性肺炎だった
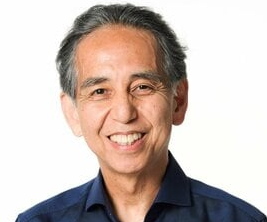
音楽フェスを作り上げ、評論というジャンルを切り開いた74年の人生に、多くの人が静かに敬意を表しています。
入院のきっかけは脳出血だった
2023年の秋、渋谷陽一さんは脳出血を起こして緊急入院します。
手術後は療養に入り、ゆっくりリハビリを続けていました。
そのニュースが出たとき、音楽業界には一瞬、緊張が走りました。
「まさか、渋谷さんが…」という声も多かったようです。
筆者自身も大学時代、バンドサークルに入っており、当時は音楽雑誌をよく読んでいました。
ロッキングオンもよく読んでいた雑誌の1つで、渋谷さんの文章には随所に体験談があったり、読んでいて楽しめる要素がたくさんあったように思います。
渋谷陽一さんは、入院後もあえて表には出ませんでした。
2024年には社長を退き、会長としてグループを支える立場に。
静かに身を引きながらも、自分がつくったフィールドはしっかり守り続けていた。
その姿に、言葉にせずとも強い意志を感じた人は少なくなかったはずです。
誤嚥性肺炎を併発し、家族に見守られて逝去
脳出血からの回復を目指していた渋谷陽一さんでしたが、2025年に入って誤嚥性肺炎を併発。
療養生活の中で、容体は少しずつ悪化していったそうです。
ロッキングオンの公式発表によると、2025年7月14日未明、自宅で家族に見守られながら息を引き取ったとのこと。
静かな最期だったことが伝えられています。
葬儀は近親者のみで執り行われ、香典や供花も辞退。
渋谷陽一さんらしい、控えめで筋の通った別れ方でした。
「ロックンロールってのは、そういうものなんだろうな」って、勝手に納得してしまうような去り方でした。
“派手じゃなくていい。言いたいことは、もう全部言った。”
そんな潔さを、最後の瞬間まで貫いていた気がします。
渋谷陽一さんの学歴と経歴まとめ:評論家から会長までの道のり
渋谷陽一さんは、ただの音楽評論家じゃありません。
雑誌をつくり、フェスを企画し、ラジオで語り、若手に背中を見せてきた人。
自分にとっては、「音楽って“聴く”だけじゃなくて“考えていいもの”なんだ」と教えてくれた先生のような存在でした。
学歴は東京都立千歳丘高校→明治学院大学(中退)
出身は東京都新宿区。高校は東京都立千歳丘高等学校に進学。
大学は明治学院大学経済学部に入学しますが、音楽への情熱が勝り中退しています。
実はこの大学時代、バンドサークルでの活動を通して「評論」ではなく「音をどう捉えるか」にこだわる視点が育ったとも語られています。
レコード1枚聴いて、2時間語れるような熱量だったそうです。
筆者自身も大学のサークルで、バンドやラジオの企画に全力を注いでいた時期がありました。
試験よりスタジオ予約、講義よりライブのフライヤーづくり。
親からは怒られましたが、渋谷陽一さんの“中退エピソード”がどこか励みになっていたのも事実です。
音楽評論家デビューからロッキングオン創業までの流れ
1971年、19歳で『ミュージックライフ』誌にて音楽評論家デビュー。
最初に書いたのはグランド・ファンク・レイルロードのレビューで、タイトルは
「枯れたロック界に水をまく放水車G.F.R.『サバイバル』について」。
この時点で、すでに“渋谷節”は出来上がっていたといっていいでしょう。
そして1972年、わずか20歳で『rockin’on』を創刊。
洋楽ロックへの深い愛情と、評論の独自性が多くの支持を集めました。
学生のとき、図書館でバックナンバーを探し出してコピーしたことがあります。
レビューの構成、タイトルのつけ方、文字数のバランスまで徹底的に真似した結果、
「君、評論家気取りか?」ってサークルの先輩に笑われたのも、今では良い思い出です。
ロッキングオン・グループの社長・会長としての経営手腕
その後、1986年には邦楽版『ROCKIN’ON JAPAN』を創刊。
以降、『CUT』『BRIDGE』『H』『SIGHT』などのメディアを次々立ち上げます。
このあたりの「好きなものを深く掘る姿勢」が、若い頃の自分にとってはものすごく眩しかった。
「音楽を聴くって、こんなにも頭を使う行為なんだ」と気づかせてくれたのが、渋谷陽一さんの文章だったと思います。
ロッキングオン・グループの経営者としても、常に“音楽の最前線”に立ち続けた存在でした。
2024年には社長職を退任し、会長に就任。
肩書きが変わっても、渋谷陽一さんの音楽への情熱は変わりませんでした。
音楽フェスを変えた渋谷陽一さん:ロックインジャパンとCDJの誕生秘話
渋谷陽一さんの功績を語るうえで、音楽フェスの存在は欠かせません。
2000年代以降、日本のフェス文化を押し上げた立役者のひとりでした。
ROCK IN JAPAN FESTIVALを始めたきっかけ
2000年、茨城県ひたちなか市で初開催されたROCK IN JAPAN FESTIVAL。
「邦楽だけのロックフェスなんて成立するのか?」と疑問視された中で、渋谷陽一さんはあえて勝負に出ました。
結果として、チケットは即完売。
“ジャパンのロック”が市民権を得た瞬間でした。
なお、洋楽偏重だった当時のフェス文化に対して、「日本のロックをちゃんと讃えよう」という挑戦でもありました。
当時のROCKIN’ONの記事に「野外フェスは、音楽を社会に開く儀式だ」という一文があり、しびれた覚えがあります。
フェスに“思想”を入れた人って、そうそういないと思います。
COUNTDOWN JAPANで示した“年越しの新常識”
続いて2003年には、年末恒例となるCOUNTDOWN JAPAN(CDJ)をプロデュース。
冬に屋内で開催されるフェスという新しい形を提示しました。
CDJの存在が、年末の過ごし方を変えた人も多いのではないでしょうか?
「紅白じゃなくて、CDJ」そんな人も少なくなかったはずです。
ちなみに初めて参戦したときは、年越しの瞬間に全会場のスクリーンが一斉にカウントダウンする演出に鳥肌が立ちました。
「これは音楽で作る年越しだ…」と、ちょっと感動してしまったんですよね。
JAPAN JAMやNO NUKESなど多彩なプロデュース実績
そのほかにも、JAPAN JAM、NO NUKES(脱原発フェス)、アート寄りのメディア展開まで、ジャンルレスに活動を広げていました。
フェスを“音楽を浴びる場所”から、“カルチャーが交わる場”へと進化させた張本人だったと言えるでしょう。
ワールドロックナウと渋谷陽一さん:27年間の声が生んだラジオ文化
渋谷陽一さんといえば、ラジオ番組『ワールドロックナウ』も欠かせません。
この番組がなければ、今の音楽リスナー文化はもう少し違ったものになっていたかもしれません。
ワールドロックナウはどんな番組だったのか?
『ワールドロックナウ』は、NHK-FMで1988年から2024年まで続いた長寿番組。
洋楽ロックの新譜を、毎週丁寧に紹介しながら深掘りする構成でした。
渋谷陽一さんの低めの声と独特な語り口で、「ただの紹介番組」では終わらない奥行きがありました。
僕らの世代にとっては、「音楽を“耳で学ぶ”時間」そのものでした。
最終回は代打DJ・伊藤政則が担当、惜しまれつつ終了
2024年3月の最終回では、伊藤政則さんが代打として登場。
SNSでは、番組終了を惜しむリスナーの声が続出しました。
「ありがとう渋谷さん」
「あなたの声があったから、音楽がもっと好きになれました」
その一言一言が、番組の持つ意味の大きさを物語っていました。
渋谷陽一さんとリスナーをつないだ“音の居場所”
この番組を通して、多くの人が音楽を知り、語り合い、共有する文化が生まれました。
渋谷陽一さんの存在そのものが、“音楽を通してつながる場”だったのかもしれません。
渋谷陽一さんの死に、音楽業界から追悼の声が続々
渋谷陽一さんの死去が報じられると、SNSや音楽メディアには追悼の声が次々と寄せられました。
その反響からも、どれほど多くの人に影響を与えてきたかが分かります。
ミュージシャンや関係者からのSNSでの声
アーティストやバンド関係者からは「人生を変えてくれた人」「音楽の楽しみ方を教えてくれた人」といった投稿が相次ぎました。
中には「ROCKIN’ON JAPANで特集されたのがきっかけでメジャーデビューした」というエピソードも。
渋谷陽一さんが与えた影響とは?
音楽をただ消費するのではなく、“批評する文化”を育てた第一人者。
言葉で音楽を語ることに意味を与えた存在だったといえるでしょう。
“音楽を論じる意味”を広げた先駆者としての評価
雑誌、ラジオ、フェス、イベント。
渋谷陽一さんがやってきたことは、いつも「音楽を広げること」でした。
その精神は、これからも多くの人の中で息づいていくはずです。
