大黒礼騎さんが死去|訃報の詳細と時系列を解説
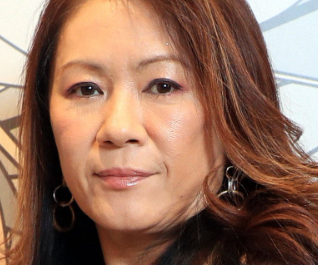
大黒摩季さんの実弟・大黒礼騎さんが、2025年9月6日の未明に亡くなったことが報じられました。
心からご冥福をお祈りいたします。
訃報は、姉である大黒摩季さんが自身のInstagramで公表。
その投稿には、家族としての深い絆と、礼騎さんへの惜しみない敬意、そして言葉にしきれないほどの哀しみがにじんでいました。
亡くなったのはいつ?報道された時期と経緯
大黒礼騎さんが天国へ旅立ったのは、2025年9月6日 午前2時31分のこと。
Instagramの投稿では、正確な時間まで丁寧に記されていて、それだけにリアリティと重みがあります。
実はその数日前、2025年8月30日には大黒摩季さんのライブを観に訪れていたそうです。
しかも翌日も一緒に過ごしていたとのことで、そのわずか数日後の出来事だったというのが信じられません。
9月3日の夕方、脳出血を再発し救急搬送。
そこからわずか3日での急逝だったそうです。
このスピード感には、筆者も驚きました。
「昨日まで普通にいた人が…」という現実、思い当たる人も多いのではないでしょうか。
死因は「脳出血」
死因は「脳出血」。
礼騎さんは、2021年にも一度、椎骨動脈乖離を発症しており、そのときは奇跡的に生還されたとのこと。
今回の再発は、誰にも予測できなかったものだったようです。
筆者のエンジニア仲間に「急に頭が割れるように痛くなった」と言って救急車で運ばれた人がいましたが、原因がまさにこれだったそうです。
仕事に没頭していると、自分の体の異常に気づくのが遅れるんですよね。
ストレス、睡眠不足、運動不足。
フリーランスの生活が長い人ほど、ここには注意が必要かもしれません。
SNSや世間の反応は?追悼の声が相次ぐ
SNSでは、大黒摩季さんの投稿に多くのファンがコメントを寄せ、「涙が止まらない」「兄妹愛に心を打たれた」など、追悼の声があふれました。
芸能界からのコメントはまだ多くは出ていませんが、ファンからのメッセージを読むと、礼騎さんの存在がどれほど温かく、人に愛された人物だったのかが伝わってきます。
また、礼騎さんの存在を今回初めて知った方も多く、「こんな素敵な人がいたなんて」と感銘を受ける人も少なくありませんでした。
一人の人生が、これだけ多くの人に影響を与えるという事実。
それ自体が、礼騎さんの「生きた証」だったのではないでしょうか。
大黒礼騎さんの職業は札幌キムラヤの社長だった
大黒礼騎さんは、札幌の老舗パン屋「札幌キムラヤ」の代表取締役社長として知られていました。
芸能界とは一線を画し、地元密着型の実業家として地道に地域に貢献されていた方です。
姉・大黒摩季さんが「自慢の弟だった」と語ったように、礼騎さんの姿勢はまさに実直そのものだったのでしょう。
札幌キムラヤってどんな会社?
札幌キムラヤは、北海道・札幌市で長年愛され続けているパン製造・販売会社です。
創業は昭和24年とされており、地元の人にとっては“ソウルフード”と呼べるような存在です。
ちなみに「キムラヤ」という名前から都内のあのパン屋を連想する方も多いかもしれませんが、直接的な関係はないようです。
とはいえ、「日本のパン文化」を広げた一角を担ったという意味では、共通点があるのかもしれません。
また、礼騎さんが引き継いでからは「うさぎのパン工房」などのブランド展開も進めていたようで、地元民の間でも好評だったそうです。
40代エンジニア視点でいうと、「会社の2代目や3代目が後を継ぐ」って、めちゃくちゃプレッシャーなんですよね。
古き良きものを守りながら、現代に合う形に進化させる。
それって、レガシーシステムのリファクタリングに近い感覚です。
「うさぎのパン工房」で売られるパンの種類とは?
札幌キムラヤの新しい顔として知られていたのが「うさぎのパン工房」。
ふんわり系から昔ながらのあんぱん系、さらには動物モチーフの可愛らしいパンまで揃っているのが特徴です。
特に人気なのは、動物の顔が描かれた「うさぎパン」。
お子さん連れの家族や観光客にも大人気で、SNSでも度々取り上げられていました。
筆者の友人(札幌在住)は、「うちの子が“キムラヤのパン屋さん行こう”って言うくらい、日常の一部になってた」と話していました。
こうした“地元密着”のパン屋さんを経営することは、ただの商売以上に“文化”を守る行為にも感じます。
父の急逝をきっかけに家業を継いだ背景とは
礼騎さんが札幌キムラヤを継ぐことになったのは、お父様が急逝されたことがきっかけだったそうです。
当時、東京で別の仕事をしていた礼騎さんは、家業の危機を前にして地元に戻る決断をしたとのこと。
この話、すごくグッときました。
「自分にしかできないことがある」と思ったとき、人は地位やキャリアを超えて動くんですよね。
エンジニアの世界でも「このシステムを守れるのは自分しかいない」と感じて、誰もやりたがらないメンテを引き受ける人がいます。
そういう人って、表には出ないけれど、本当に尊敬されるんですよ。
大黒礼騎さんも、まさにそんな存在だったのではないでしょうか。
大黒摩季さんと弟・礼騎さんの兄妹関係
大黒摩季さんと大黒礼騎さん。
二人は非常に仲が良く、特に近年は家業や家族のことを通じて、より深く絆を育んでいたようです。
SNSやインタビューなどでもたびたび礼騎さんの名前が登場しており、「弟というより“戦友”みたいだった」と語られることもありました。
大黒摩季さんの家族構成と兄妹エピソード
大黒家は、札幌市内のパン屋を家業とする一般家庭。
お父様が創業者であり、礼騎さんが後を継ぎました。
大黒摩季さんが幼い頃から、礼騎さんと一緒にパンを作ったり、お店の手伝いをしていたそうです。
当時から礼騎さんは器用で真面目、何よりも優しさのかたまりのような子だったそうで、姉の摩季さんにとっても心の支えだったようです。
私の仲間でも「うちの兄弟は全然しゃべらんぞ?」っていう人もいれば、「毎週電話してる」という人もいますが、礼騎さんと摩季さんの関係は明らかに後者。
仕事に生きる人間ほど、家族との絆が最後の砦になる。
礼騎さんの生き方を見て、そう感じた方も多いのではないでしょうか。
公式コメント全文|大黒摩季が語った「愛弟」の姿
大黒摩季さんはInstagramにて、礼騎さんへの想いを長文で投稿しています。
そこには、弟としての礼騎さん、経営者としての礼騎さん、家族を守る柱としての礼騎さん、すべての姿が詰まっていました。
コメントの中で語られた「“兄妹であって良かった”と思える関係」って、実はなかなか築けないんです。
親しさや遠慮、責任と信頼、いろんな感情が混ざり合うからこそ、そこには“絆”があるんだと感じました。
「家族の絆」を感じる投稿と写真の紹介
摩季さんの投稿には、礼騎さんとのツーショットや、家族での集合写真などもアップされていました。
どれも気取らず、自然体で、まさに“家族のあたたかさ”がにじみ出ているものばかり。
読者の中には「まるで自分の家族を見てるみたいだった」と共感した方も多いはず。
こういう“ちょっとした幸せの記録”が、思い出として残るんですよね。
そして何より、その写真の中の大黒礼騎さんは、とても優しい表情をされていました。
人は、亡くなってからその人の「在り方」をあらためて見つめ直すことがあります。
礼騎さんの姿は、まさに“生き様そのもの”でした。
次は「死因となった椎骨動脈乖離とは?専門的に解説」という見出しに進みます。
このまま続けますね!
死因の発端となった椎骨動脈乖離とは?専門的に解説
大黒礼騎さんの死因は、脳出血です。
これは実は誰にでも起こりうるものです。
特に働き盛りの40代〜50代の男性に多く見られるとされています。
どんな病気?発症のメカニズムとリスク
椎骨動脈とは、首の後ろ側を通って脳へと血液を送る重要な動脈です。
この血管が何らかの理由で裂けてしまうことを「乖離」と呼びます。
乖離が起きると、血管の内側に血が溜まり、血流を妨げてしまいます。
その結果、脳への血流が不足したり、破裂して出血したりと、非常に危険な状態になるのです。
「突然、今までにないレベルの激しい頭痛が来たら、すぐ病院へ」というのが鉄則だそうです。
エンジニア職は長時間同じ姿勢で作業することが多く、首や肩に負担がかかるのも一因といわれています。
体は機械と違って部品交換できません。
日頃のメンテナンス、大事ですね。
症状・前兆は?早期発見の重要性
椎骨動脈乖離の初期症状は、以下のようなものが報告されています。
- 突然の激しい頭痛(特に後頭部)
- ふらつきやめまい
- 片側の手足のしびれや力が入らない
- 言葉がうまく出てこない
実際に、礼騎さんも数年前にこの病気を一度経験しており、その際は回復されていました。
ただ、再発は予測できず、今回は短期間で症状が悪化してしまったようです。
筆者の知人にも「肩こりだと思って放置してたら脳梗塞だった」というケースがありました。
ちょっとした違和感を「まぁ大丈夫」と流すのは、もはや時代遅れです。
再発リスクや予防法について
椎骨動脈乖離は、再発することもあります。
特に以下のような生活習慣がある方は注意が必要です。
- 慢性的なストレス
- 睡眠不足
- 高血圧や糖尿病などの基礎疾患
- 姿勢の悪さ(猫背やスマホ首)
- 首を急にひねる動作(ストレッチなども注意)
予防の基本は、とにかく無理をしないこと。
仕事中も1時間ごとに休憩を挟む、首まわりを軽く動かす、睡眠時間をしっかり取る。
派手じゃないけれど、地道な習慣が命を守ってくれるんです。
