エムポックス(サル痘)感染が国内初確認!何が起きた?
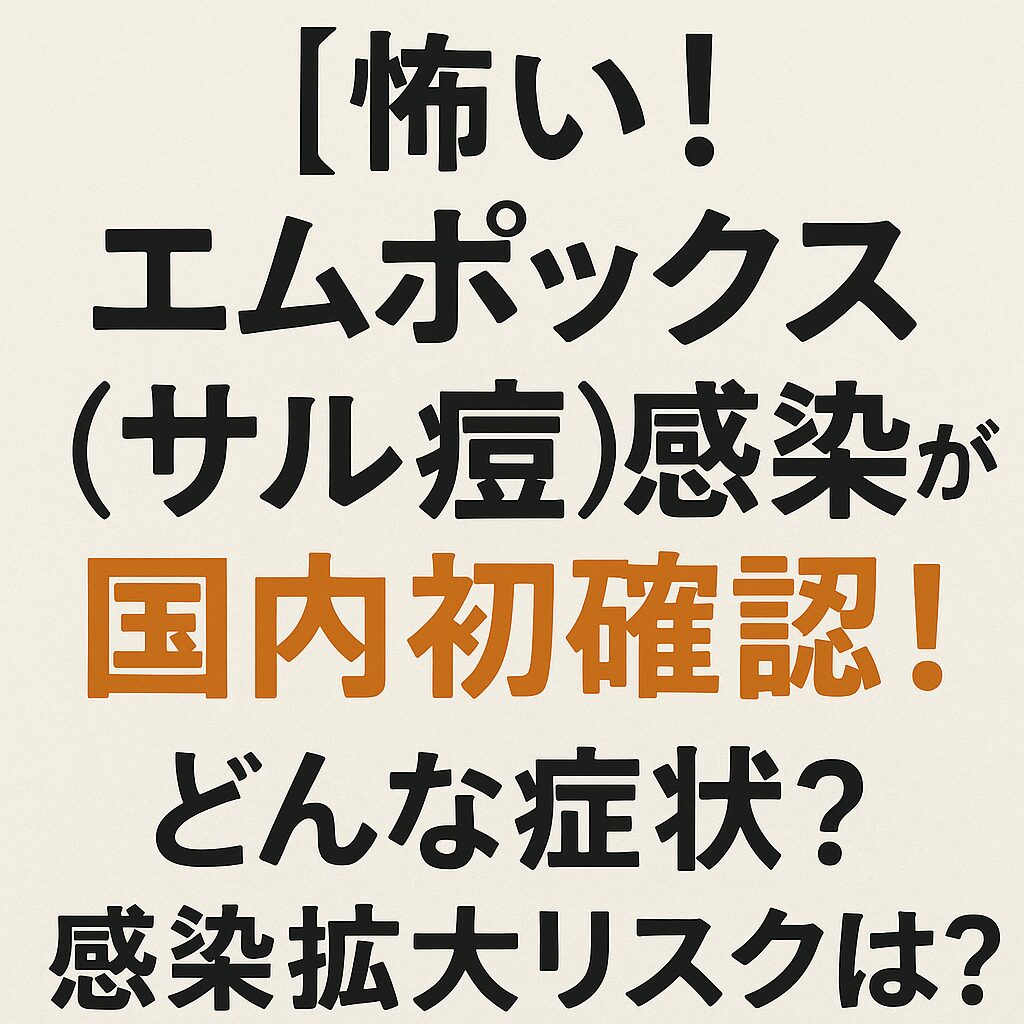
このニュース、正直ちょっとゾッとしました。
なぜなら、感染していたウイルスは「クレードIb型」というタイプで、国内では初めて報告されたものなんです。
僕自身、以前にアフリカ出張の話があった時、ちょっと怖くて断ったことがあるんですが、
その判断、今になって「意外と正解だったかも…」と思ってしまいました。
この女性は、帰国後に発熱や発疹などの症状が出て、病院で検査を受けて感染が判明したとのこと。
症状自体は軽めで、容体も安定しているそうですが、「ウイルスの型が変わってきてる」という点がじわじわ怖いですよね。
実際、厚労省も「発疹や熱が出たら、海外渡航歴を伝えて医療機関へ」と注意を呼びかけています。
出張や旅行のあとに体調を崩すのって、よくある話ですが…これからは甘く見ちゃダメだなと痛感します。
ちなみにエムポックス、正式にはサル痘と呼ばれていた病気で、もともとはアフリカの一部で確認されていた感染症です。
それが2022年頃から世界的に広まり、今では“誰がどこで感染してもおかしくない”状況になりつつあります。
このニュースを見て感じたのは、「もう日本も安全圏じゃないな」という現実。
たとえ一部の地域や人に限った話でも、社会全体として備えは必要なんだと思います。
どんな症状?感染拡大リスクをわかりやすく解説

エムポックスの症状って、正直ちょっと想像しづらいですよね。
「サル痘って言われても、なんだか遠い病気っぽいなあ…」と思っていたのですが、内容を知れば知るほど、“現代人にとってリアルに脅威”な感染症だと実感します。
まず、症状の流れですが——
最初は発熱、頭痛、リンパの腫れ、筋肉痛などが数日続きます。
その後、ポツポツと発疹が出てきて、それが水ぶくれや膿疱(のうほう)になり、最後はかさぶたになって剥がれ落ちる…という流れ。
この一連の流れがだいたい2〜4週間かけて続くそうです。
厄介なのは、発疹が顔や体だけでなく、口の中や性器、目のまわりなど、デリケートな場所にもできる点。
発疹の場所によっては、日常生活にもかなりの支障が出る可能性があります。
しかも、最近は「発熱などの前ぶれナシで、いきなり発疹から始まるケース」も増えているようです。
これはちょっと厄介ですね。風邪っぽい前兆がないぶん、気づいたらもう人にうつしてた…なんてこともありそうです。
個人的には、こういう「見た目でわかりにくい症状の感染症」って一番警戒すべきだと思っています。
発熱も咳もないのに、実は自分が感染していた――そんな状況、在宅ワークじゃない職場では普通に起こりえますからね。
さらに感染拡大のリスクについてですが、飛沫(ひまつ)による感染もあれば、皮膚の傷や体液との接触でもうつるとされています。
特に寝具やタオルの共有など、家庭内でも油断は禁物です。
ざっくりまとめると、エムポックスは「症状が地味だけど長引く」「感染力がジワジワ系」「対策しづらい部類の病気」だと感じました。
怖がりすぎる必要はないですが、「知って備える」ことは誰にとっても損じゃないはずです。
次は、エムポックスの“見えない脅威”とも言える、潜伏期間や感染経路について見ていきましょう。
知らないうちに感染していた…なんて事態、避けたいですよね。
エムポックスの潜伏期間と感染経路は?
エムポックスのやっかいなポイントのひとつが、「潜伏期間の長さと幅」です。
だいたい6〜13日が平均とされていますが、最大で21日…つまり3週間も潜伏する可能性があるんです。
これ、地味に怖くないですか?
例えば出張や旅行で感染して帰国しても、2週間以上何も起きず、忘れた頃に発疹が出てくる、なんてこともあるわけです。
感染経路についても、ちょっとややこしい。
基本は「感染者の皮膚の病変・体液・血液との接触」とされていますが、これってつまり、
・性的接触(とくに皮膚と皮膚が触れる場面)
・感染者が使った寝具やタオルの共用
・顔を近づけての長時間の会話(飛沫)
などでもうつる可能性がある、ということです。
ただ、空気感染までは確認されていないので、コロナのような“ただそこにいるだけでうつる”感じではないようです。
でも油断できないのが、「本人が無症状でも人にうつすリスクがある」とされている点ですね。
正直、ここまで読んで「コロナより怖くない?」と思った方もいるかもしれません。
僕も最初はそう感じました。けれど、感染力や致死率ではコロナより低いという専門家の意見もあるので、
必要以上にビビることはないかなとも思っています。
ただ、「潜伏期間が長い・接触で感染する・自覚症状が遅れることもある」という三拍子がそろっている以上、
“自分が媒介者になってしまう”可能性を常に意識しておくのは大事ですね。
感染を防ぐための予防策とは?
どんな感染症も「予防に勝る治療なし」ですが、エムポックスに関してもまさにその通りです。
とはいえ、「じゃあ何をすればいいの?」と聞かれると、意外とイメージが湧きづらい人も多いはず。
まず基本のき、接触を避けること。
エムポックスは皮膚や体液を通じてうつるので、発疹がある人との密接なスキンシップは避けた方が安心です。
タオルや寝具の共有もNG。家族であっても、症状がある人とはちょっと距離をとった方がよさそうです。
次にマスクの着用。
飛沫感染のリスクがある場面(特に会話が多い場所)では、いまだにマスクが役に立ちます。
感染者本人も、発疹部分を覆うガーゼを使うことで、周囲にうつすリスクを下げることができると言われています。
あと、これちょっと大事なポイントなんですが、
「原因不明の発疹があるときに性行為を避ける」ってのも、めちゃくちゃ重要なんです。
海外ではこのルートでの感染が多かったこともあり、厚労省もハッキリ警告しています。
個人的に思うのは、予防というのは「行動を我慢すること」ではなくて、
「一歩先を想像する習慣」なんじゃないかと。
出張前に体調を整えておくとか、旅行先で体調が変だなと思ったら無理せず休むとか、
ちょっとした心がけで防げることって、実はたくさんあると思うんです。
手洗い・うがい・清潔な生活。
こう書くと小学生の保健の授業みたいですが、やっぱりこの辺が一番強い。
昔ながらの習慣って、結局いちばん頼りになりますよね。
さて、ここまで予防の基本を押さえたところで、
次はちょっと専門的な話に入っていきます。
ニュースでも注目された「クレードIb型」って一体何者なのか?
そして、それがどれだけ怖いのかを見ていきましょう。
クレードIb型って何?重症化リスクは高い?
今回のニュースで注目されたのが、「クレードIb型」という聞き慣れないウイルスの型。
一見すると専門用語に見えますが、ざっくり言えば“エムポックスの進化系”のひとつです。
エムポックスのウイルスは、大きく分けてクレードIとクレードIIという2種類の系統があります。
そのうちクレードIのほうが、症状が重くなりやすいと言われています。
そして、今回感染が確認された「クレードIb型」は、そのクレードIの中でも比較的新しい型なんです。
特徴的なのは、この型が「性的接触によって拡大した」と推定されている点。
特定の地域や集団で広がっていた従来型とは違い、より“人から人へ”うつりやすくなっている可能性があるんです。
じゃあ、重症化しやすいの?という疑問ですが、
今のところクレードIb型の致死率は1%未満とされています。
ただ、免疫力が低い人や、基礎疾患を持つ人は重症化のリスクがあるので油断は禁物です。
また、海外では「皮膚の合併症」や「目の病気(角膜炎)」を引き起こすケースも報告されており、
単なる“ちょっとした発疹”で済む病気ではないことは確かです。
個人的にこの件でハッとしたのは、
「新しい型だからって、すぐに全貌がわかるわけじゃない」という点。
ニュースで“重症化リスクは低い”と聞いても、それは“今わかっている限り”の話なんですよね。
技術職の経験上、新種とかバージョンアップされたものって、最初は見えない不具合が潜んでることが多いんです。
だからこそ「新しいウイルス型が出た=一応気をつけておこう」くらいの心構えが大事だと思っています。
ワクチンの効果と接種の必要性について
エムポックスのニュースが話題になるたび、「ワクチンってあるの?」「打ったほうがいいの?」という疑問がつきものです。
結論から言うと、日本ではエムポックスに対して効果があるとされるワクチンが、すでに承認されています。
それが「乾燥細胞培養痘そうワクチン(LC16m8)」というもの。
これはもともと天然痘のために開発されたワクチンですが、エムポックスにも有効とされています。
現時点では、一般の人が気軽に接種できる状況ではありません。
医療従事者や、感染リスクが高いとされる人などに限定して、国が対応を進めている段階です。
では、私たち一般人にとっては無関係なのか?
そんなことはありません。
このワクチンは、発症前に接種することで予防効果があるだけでなく、
感染後でも発症前に接種できれば、症状を軽くできる可能性があるとされています。
つまり、「いざというときの備え」になるわけですね。
個人的には、今のところ焦って接種を求める必要はないと思っています。
ただ、もし今後、感染が拡大して「希望者に接種枠が広がる」なんて動きが出てきたら、
情報を早めにチェックして、自分に必要かどうかを冷静に判断したいところです。
特に、医療・介護・接客業など「人との距離が近い仕事」をしている人は、
ワクチンの対象になりやすい可能性があるので、動向は見ておくといいかもしれません。
ウイルスは見えないからこそ、備えがすべて。
その意味で、ワクチンは“最終手段”でありながら、安心材料にもなる存在だと感じます。
