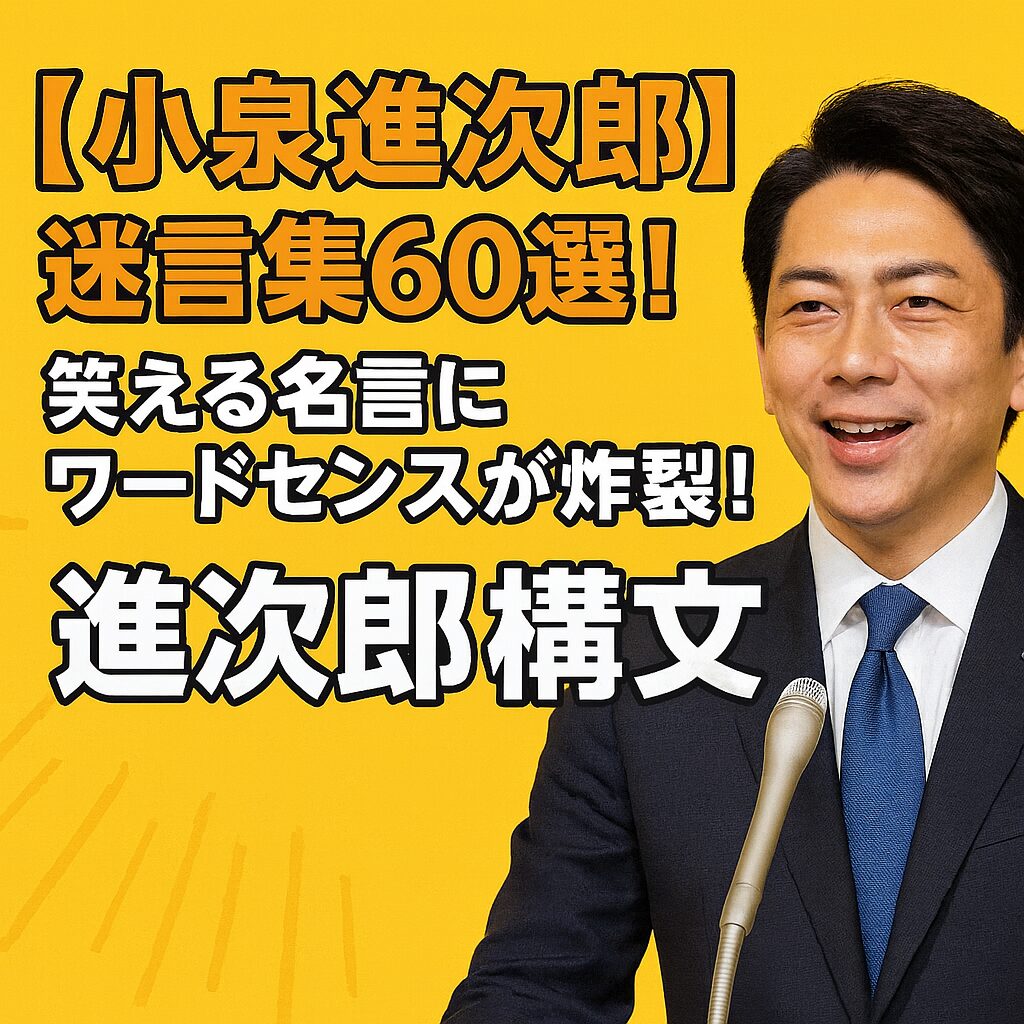
小泉進次郎の迷言集60選!笑える名言たちを一挙紹介!
この見出しでは、誰もが一度は聞いたことのある「進次郎構文」の中から、厳選した名言・迷言をジャンル別に紹介していきます。
言葉のインパクトはもちろん、文脈やシチュエーションまで含めて、どこかクセになる不思議な魅力があるんですよね。
それぞれの迷言に対して、40代システムエンジニアである筆者目線のツッコミや感想も交えながら見ていきましょう!
名言①〜⑩:思わずクスッと笑う不思議な日本語
たとえばこちら。
・初めてお会いした時は初対面でしたね。
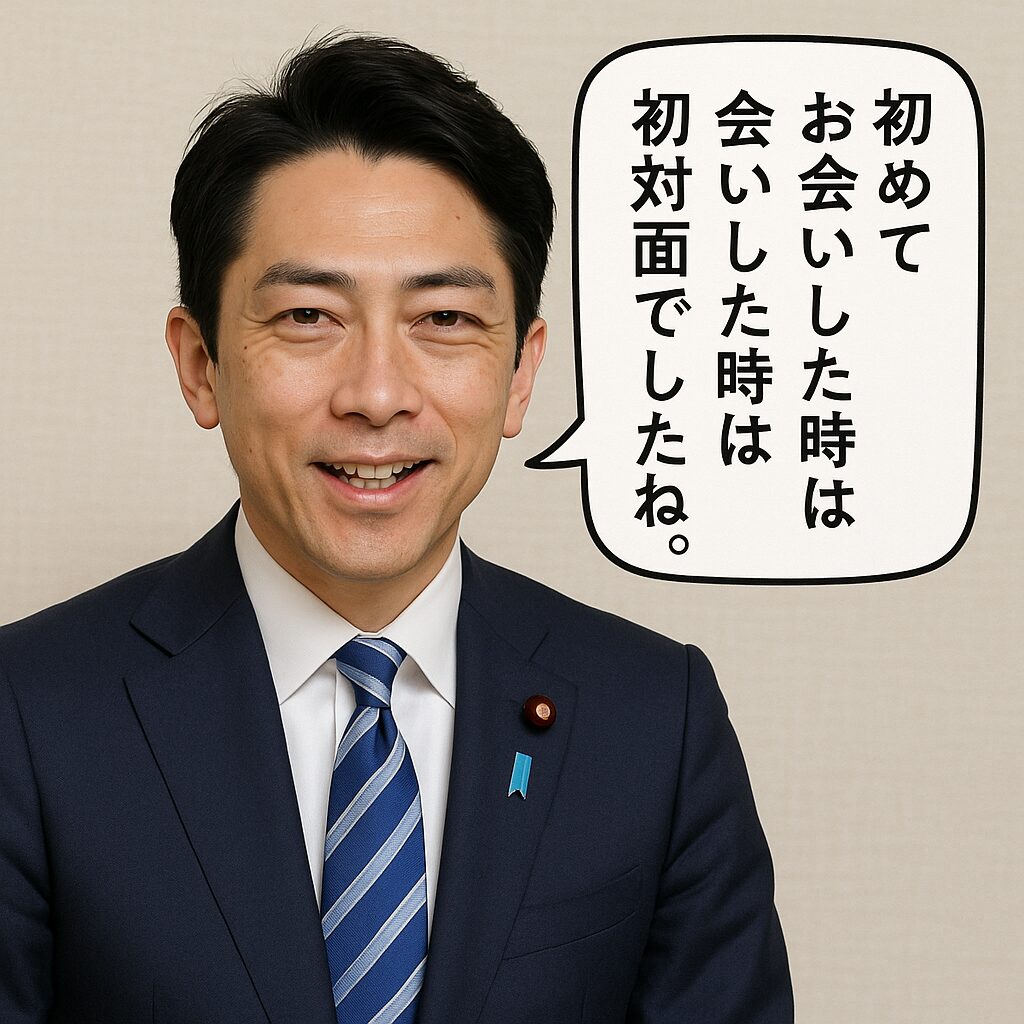
→そりゃそうだ、としか言いようがありません。完全なるトートロジー。でも言われたらなぜか妙に納得してしまうあたり、進次郎構文の本領発揮です。
・1分が60秒のように感じた。
→え、どういう意味…? いや、それが普通ですって。思わずツッコミたくなりますが、まるで時空がねじれたような感覚すら覚えます。
・サーフィンやったことあるの? じゃあ経験者だね。
→このシンプルな構文に、「経験とは何か」みたいな哲学を感じてしまうのはSEの職業病でしょうか。
・この時計、時計回りですね。
→40代のシステムエンジニアとして、”逆時計回り”という概念もあるにはありますが…普通は時計回りです。
・みかんは遠くより近くで見たほうが大きいね。
→確かに。物理の話としては正しいんですが、それを“気づき”として共有するセンス、なかなかです。
・水には豊富な水分が含まれていますからね。
→プログラミング言語で書いたら「water.contains(water)」みたいなコードになりそうです。
・笑うと笑顔になるんです。
→このあたりになると、もう一種の詩ですよね。論理とか意味じゃなくて、空気を味わう感覚に近いです。
・お兄ちゃんのほうが年上なのかな?
→進次郎さん、”お兄ちゃん”って時点でほぼ答え出てますよ。
・金属の部分とプラスチックの部分で素材が違うんですね。
→そのまんまですが、こういう素直すぎる観察眼も嫌いじゃないです。技術職としては、むしろ共感すらあります。
・このおにぎり、お米の味がしますね。
→食品レビューだとしたら0点ですが、小泉進次郎さんが言うとほっこりしますね。
どれも一見すると「えっ?」と戸惑ってしまいますが、改めて振り返ると妙に癖になってきませんか?
このあたりの言葉たちは、意味を超えた“味”があると思います。
名言⑪〜⑳:哲学的すぎて意味不明?進次郎語録の魅力
ここからはさらにレベルアップした“進次郎ワールド”を紹介します。
言葉の意味を考えるほどに深みにハマっていく、ある意味「哲学的」な名言たちをどうぞ。
・「はい」か「YES」で答えてください。
→強制的に同意を引き出す圧。ここまで明るく言い切れる政治家、なかなかいません。
・球って意外に丸いんですね。
→球とは…? 小泉進次郎さんにとって「常識」は再発見の対象なのかもしれません。
・試合が終わったら、そこで試合終了なんですよね。
→スラムダンク的な響き。名言風に聞こえてしまうのが悔しい。
・この映像を観ている30年後の僕へ。今何歳ですか?
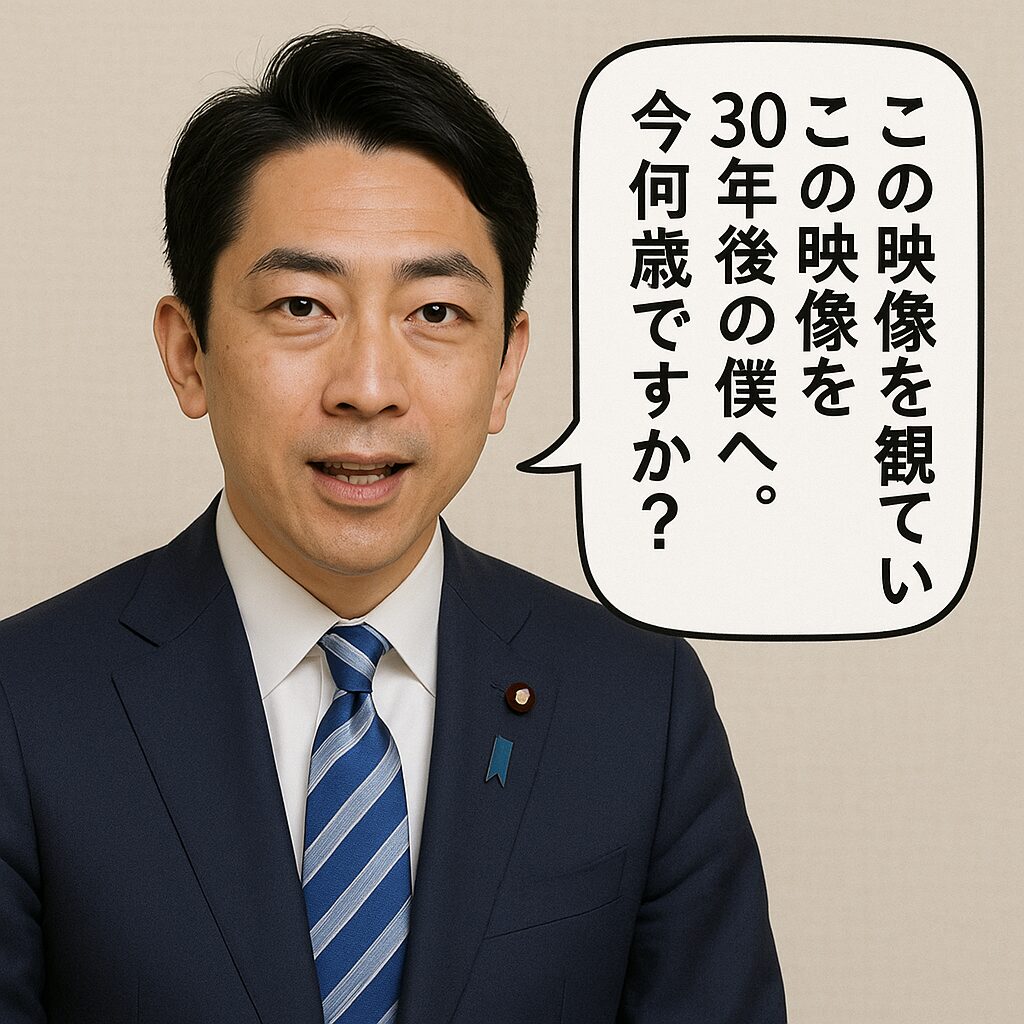
→時間軸を超えた問いかけ。映画『インターステラー』か何かでしょうか。
・無意識って気づかないもんなんですね。
→はい、無意識とはそういうものです。深いんだか浅いんだか…。
・朝食はいつも朝 食べます。
→「いつも朝」以外の選択肢があるのか、という哲学的問い。
・この試合、勝ったチームが勝者なんですね。
→定義を説明する力強さ。まるでプログラミングで「if win then winner」って書いてるような感覚です。
・お金払ったらタダでもらえたんですよ。
→この矛盾こそが日本のサービス文化の極致かもしれません。
・色を変えるだけで色違いになるんですね。
→この発想、デザイン会議で出されたら全員一度黙ると思います。
・このおにぎり、お米の味がしますね。
→二度目の登場ですが、やはり言っておきたい名言。
こうして並べてみると、論理のようで論理でない。説明のようで説明になっていない。
でも、それがどこか心に残るのが不思議です。
次は、「ここまでくると芸術!」と思える発言をご紹介します!
名言㉑〜㉚:ここまでくると芸術!小泉ワールド全開
もはや迷言というより“芸術表現”に片足突っ込んでいる発言を集めました。
システムエンジニアとして長年ロジカルな世界にいた筆者からすれば、これらはある意味“対極”の世界観。でも、だからこそ惹かれるのかもしれません。
・環境ね、これは生き物ですね。つまり、環境とは生きているものではないかと。
→「で、どっちなの?」と思わずツッコみたくなります。
・私は皆さんに12時の7時間後は7時であり、19時でもあるということを真剣にお伝えしたい。
→タイムゾーンの話かと思いきや、ただの時刻の説明でした。
・日本に戻ってきてビールを飲んだ時こう思ったんです。今僕は日本のビールを飲んでいるんだなって。
→そのまんま。でも、言葉にしたくなる感動って、ありますよね。
・年の瀬、師走。こういう言葉を聞くといつも思います。もうすぐ新年だなと。
→うん、たしかに。でも言わない。普通は言わない。
・私はいつも思ってました。国分寺は西国分寺の東にあるということを。
→Googleマップ的には正解。だけど、それを“思い続ける”意味とは。
・サッカーはね、勝ち負けを争うゲームじゃないんです。制限時間内に相手ゴールに何本シュートを決められるか、そのほうが重要なんじゃないかと。
→得点で勝敗が決まるんですよね、サッカーって。
・渋滞してない道ならすいているんじゃない?
→…うん、それはつまり、すいてる道。
・鳥って歩く時は飛ばないんだ。
→たしかに。日常の中の“再発見”の鋭さには感心します。
・犬の散歩はいつも犬と一緒です。
→この当たり前すぎる光景にも感謝を込めているのかもしれません。
・こんなに蕎麦を焼いたら焼きそばになっちゃうよ。
→語感だけで笑える、進次郎さんらしい“ダジャレ構文”。
名言㉛〜㊿:語彙センスが迷子!?深読み禁止の言葉たち
ここでは、「いや、なんとなく言いたいことは分かるんだけど…!」と、ツッコミたくなる迷言を中心に集めました。
論理的に処理不能なものが多く、もはや直感で受け止めるしかない世界です。
・力をパワーに。
→これはもう哲学。出力を変換してるつもりなんでしょうか。最初からパワーのはず。
・両手で抱くと手がふさがるね。
→……うん。そこに何かを足したい気持ちは分かります。でも言葉にするとシュール。
・眠くない時って眠れないですよね。
→そりゃそうだ、の最たる例。でも、共感してしまう不思議。
・雪が積もるって事は、雪が降っているって事なんですよ。
→まさに実況中継。伝えたくなる気持ちは分かります。
・自由があるのが自由民主党。自由がないのが民主党。
→絶妙な語呂と語感。内容よりリズムで押し切るスタイルです。
・誕生日なんですね。私も誕生日に生まれたんです。
→やっぱり誕生日って、そういう日です。
・夜景を見るなら、断然夜をオススメしますよ。
→昼間の夜景には何かあるんでしょうか。ちょっと興味出てきました。
・野球部員だった私は水筒を使っていたけど、環境配慮の観点で水筒を使っていなかった。
→使ってるのか使ってないのか、どっちかにしてほしい。環境対応あるあるかも?
・政治に無関心であることは、政治に無関心のままでいられると思います。だけど、政治に無関係でいられる人はいません。
→構文がややこしいけど、メッセージ性は妙に刺さるんですよね。
・調査では増えているから、増えたかどうか調査する。
→ループ構文。SE的には無限ループを警戒してしまいます。
3人家族でマスク2枚なら、1枚足りないんですよ。
→2020年「アベノマスク」配布時の記者対応にて。言わずもがなの計算を堂々と発言。
ハローワークに午後から行く予定、ということは無職なんですね。
→学生とのやり取りでの一幕。状況説明がそのまま本人の口から。
何事も一回やってみてください。次にやる時は二回目になりますから。
→インタビューにて発言。前向きなのにジワジワ来る構文代表例。
緊張して困る時は、全力でリラックスすればいいんだ。
→アドバイスのようでいて、ハードルが高すぎる名言。
くっきりした姿が見えているわけではないけど、おぼろげに浮かんできたんです。46という数字が。
→2019年選挙報道番組で発言。ネットでは“予言構文”として拡散。
辞任するとは言ったが、辞任するとは言ってない。
→辞任会見での実際の発言。言葉の綾と論理がぶつかり合う一言。
地元がホームタウン。
→地方講演会での発言。意味は通じるけど、言い換えに驚き。
明日祝日という事は、休日なんですね。
→これまた説明不要な解説構文。聞いた方が混乱するパターン。
日本で1分が過ぎている間にもアフリカでは60秒が経過している。
→時差や地球規模を意識していたはずが、結果的に構文化。
誠実に答えないなんて、不誠実ですよ。
→会見で真剣に語った場面。内容は正論なのに響きが構文そのもの。
迷言の“味わい深さ”がどんどん深まってきましたね。
次は、さらに飛び抜けた10選を紹介します!
名言51〜60:もうツッコミも追いつかない!?脳内混乱の進次郎構文
ここまでくると、もはや“進次郎語録”というより“ことわざ”のような風格。
読むだけで脳が混乱する、最上級レベルの迷言たちです。
・打倒!ドンキホーテ。打倒!パプリカ。
→対象が広すぎて背景が見えませんが、なんだか勢いだけで説得力ありそうに聞こえるから不思議です。
・今月39歳の誕生日を迎える訳ですけれども、来年は40歳になるという事です。
→成長の記録にしては淡々としすぎていて、逆におかしい。
・未成年飲酒なんて子供のすることですよ。
→その通りなんですが、言い回しがややこしい。合法と違法の間をさまよってます。
・水筒を使っていたけど、水筒を使っていなかった。
→再登場。これはやっぱり説明不能。タイムパラドックス的な何かを感じます。
・見えない、というご指摘は、私自身の問題だと反省をしている。
→“見えない反省”シリーズの一環。誠実なんだか何なんだか。
・セクシーに過ごしたい。
→環境問題について語った中での発言。コンテキストの衝撃でネット民騒然。
・水と油も混ぜればドレッシングになる。
→たしかに。でも混ぜなければ永遠に交わらない。深いのか軽いのか分からない名言。
・悲観的な考えしか持てない人口1億2千万人の国より、将来を楽観し自信に満ちた人口6千万人の国の方が成功事例を生み出せるのではないか。
→一理あるけど、人数で割り切れる話ではないような…。
・今のままではいけないと思っています。だからこそ日本は今のままではいけないと思っている。
→繰り返しで強調してるはずなのに、意味が動いていない。
・言葉には体温と体重がある。測れないけどある。
→理系脳が一瞬バグる名言。でもなんとなく分かる気もしてしまう。
笑わせてくれるだけでなく、考えさせられるところもある。
次は、この進次郎構文がSNSでどう拡散されているのか、みんなの反応を見ていきます!
小泉進次郎の進次郎構文とは?意味不明だけどクセになる理由
ネット界隈で“進次郎構文”と呼ばれるようになった言葉たちには、ある特徴があります。
ここでは、その構造やユーモアの理由、SNSでウケる背景を、40代エンジニアの視点も交えて見ていきましょう!
進次郎構文の特徴:AはAである式のトートロジー
進次郎構文の大きな特徴は「同義反復(トートロジー)」です。
たとえば「笑うと笑顔になる」「勝ったチームが勝者」など、意味としては自明なのに“言葉にする”ことで妙に深く感じる。
プログラム言語の世界でいうと if (A) then A のようなコードを延々と書いてるようなもの。
でも、それを“人間の会話”として聞くと、なぜかクセになる不思議な構造です。
進次郎構文が笑える理由:文脈と論理のズレ
日常会話に馴染むようで馴染まない、この“ズレ”が笑いのポイントです。
エンジニア的に言えば、インプットに対して「予測外のアウトプット」が返ってくる仕様みたいなもの。
想定通りじゃない分、毎回リスナー側の脳内が「?」で埋め尽くされていく感覚がクセになります。
ネットで愛される進次郎構文:パロディ化とSNS拡散
Twitterでは「#進次郎構文」のハッシュタグがあり、ユーザーによるパロディも盛んです。
「バナナはバナナの味がする」など、もはや“進次郎ごっこ”状態。
動画やTikTokでもモノマネが人気で、彼の発言が「一種のエンタメコンテンツ」化しています。
言葉の力って、ここまで届くんだな…と感心すら覚えます。
SNSで話題になった小泉進次郎の迷言・名言まとめ
SNSがここまで普及している今、小泉進次郎さんの迷言は瞬く間にネットに拡散され、多くの人の笑いとツッコミを誘っています。
ここでは、TwitterやTikTokなどで話題になった名言と、それに対するユーザーの反応を紹介します。
Twitterでバズった発言ベスト5
- 「初めてお会いした時は初対面でしたね」
→「この発言、宇宙を感じる」とツイートされ3万いいね越え。 - 「水には豊富な水分が含まれていますからね」
→“水界の進次郎”としてネタ化。ミネラルウォーターのCMパロディまで作られる始末。 - 「お兄ちゃんのほうが年上なのかな?」
→「タイムトラベル物の設定かと思った」とツッコミ殺到。 - 「環境ね、これは生き物ですね」
→環境省時代の発言。環境の定義を再構築する気なのかと話題に。 - 「お金払ったらタダでもらえたんですよ」
→“PayするとFreeになる”という新たな経済理論誕生の瞬間として大ウケ。
TikTokやYouTubeでも大人気の迷言シーン
TikTokでは、進次郎さんの発言を切り抜いた「名言集ボイス」がトレンド入り。
音源に合わせて表情を変える“口パク系”動画が大量に出回っています。
YouTubeでは“進次郎構文ランキング”という動画が複数アップされていて、コメント欄では「これ見て元気出た」という声も多いんです。
SNSユーザーの反応:称賛?皮肉?それとも愛?
面白いのは、SNSでの反応が単なる批判や揶揄だけではないところです。
「なんか憎めない」「無意識の天才」「一周回って好き」など、半ば愛されキャラとして定着している様子。
発言自体は意味不明なことも多いですが、それを笑って受け止められる空気感がSNSにはあるんですよね。
政治家らしからぬ発言が支持される理由とは?
小泉進次郎さんの発言には、いわゆる“政治家らしさ”がありません。
けれど、だからこそ支持される——そんな不思議な現象が起きているように感じます。ここではその理由について、40代エンジニア視点も交えながら分析してみます。
政治とエンタメの境界線が曖昧に
最近は「政治もエンタメの一部」みたいに捉えられることが増えてきましたよね。
発言内容よりも、キャラ・話題性・親しみやすさが評価される時代。
小泉進次郎さんはその文脈にぴったりハマる存在です。
システム開発でも「仕様よりUX(体験)」が重視されるように、政治家にも“印象”が求められる。そういう時代なんだと感じます。
発言の「ゆるさ」がもたらす親近感
ロジカルに詰めるタイプの政治家と違い、小泉進次郎さんの発言はとにかく“ゆるい”。
だけどその“ゆるさ”が、妙にリアルなんです。
完璧じゃない人間味が見えて、かえって好感が持てるというか。
SE仲間で「完璧主義すぎて怖い上司より、ちょっと抜けてる人のほうが相談しやすい」って話、よく出ます。あれと同じかもしれません。
小泉進次郎の“魅せる政治家像”とは?
小泉進次郎さんは、演説中もカメラの位置や受け手のリアクションを意識して話している印象があります。
一種の“パフォーマンス”としての政治を理解している。
意味よりも“響き”を届けることに全振りしてると感じることも。
まるで広告コピーのようなリズム感ある言葉が、耳に残る理由かもしれません。
